内村鑑三
Uchimura Kanzou
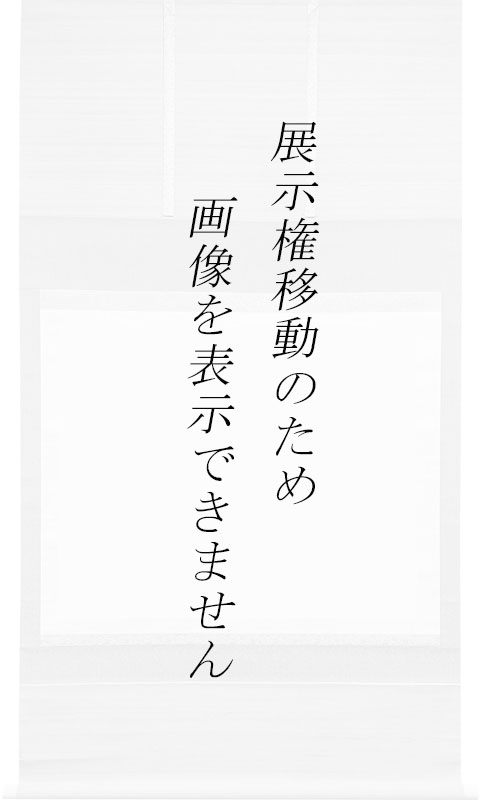
- 作家名
- 内村鑑三 うちむら かんぞう
- 作品名
- 書状
- 作品詳細
- 掛け軸 紙本水墨 緞子裂 合箱
本紙寸法 80 ×50.6
全体寸法(胴幅)88.7×163㎝ - 註釈
-
明治24年1月、第一高等中学校の講堂で、前年に天皇の詔勅として発布された教育勅語の拝読式が行われ、当時同学の嘱託教員であった内村鑑三は、教員生徒のなかで一人、教育勅語に向かって敬礼をしなかった。そのことが天皇に対し不敬であるとして、教員生徒から糾弾され、さらに社会問題化した世に言う「内村鑑三不敬事件」について、正宗白鳥が『内村鑑三』に次のように書いている。
『基督信徒の慰め』は、筆者が一生のうちに、最も苦難を嘗めた時の作品で、今日これを読み、明治二十年代の日本の世相を顧み、また筆者の身辺の事情や心理状態を追懐すると、人生について甚だ味い深い思いがされるのである。例の不敬事件の事である。(中略)益本藤澤共著の『内村鑑三傳』によって見ると、この事件は、本願寺系統の雑誌に於て、針小棒大に書き立てられ、諸新聞雑誌に転載されて、ますます大騒ぎになったらしい。「一高に於ける教育勅語拝読の式場、教員内村鑑三は、他の生徒教員がいづれも粛々として敬礼を盡(つく)すにも拘わらず、一人傲然として更に敬礼せざる状の如何にも不遜なりしにより、生徒は大に憤慨し、厳しく内村を詰りしに、彼は傲然として、我は基督教者なり、基督教の信者はかゝる偶像や文書に向かって礼拝せず、又礼拝するの理由なしと答えたるより、生徒はますます激し、同校長に迫り、校長も捨置かれぬ事なりとて内村に問うところあり、内村も同教徒と協議の上、前非を悔いて礼拝することになり(中略)・・・・」云々と報道されたのであるが、事実はこれほどの大袈裟なものではなく、「一人傲然として」云々は記事の誇張も甚しく基督教を傷つける手段に利用したのだと「内村傳」では言い訳してある。内村も後日、世評に対してさまざまな理由を付けて弁解している。「世が尊影に対し奉り敬礼せざりしとは全く虚説に過ぎず・・・・余は礼拝とは、崇拝の意にあらずして、敬礼の意なる事を、木下校長より聞きしにより、喜んで之をなせり。又爾来もこれをなすべきなり・・・・余は奸賊として放逐せられざりしなり。」と云ったりしている。大山鳴動鼠一匹と云ったような、たよりない次第である。しかし、彼が或る所で文学講演をした時、談、カーライルの作品に触れ、「自分は古本屋で、カーライルのクロンウエル傳を一円で買って来て読んで、大に感激して、自分は権威者に対して頭を下げまいと決定した。」と笑いを洩らしながら云ったのが、私の胸に響いた。(中略)ところで、この不敬事件 ― ちょっと頭を下げるとか下げぬとか云う事が、内村及びその家族の実生活に容易ならぬ悪影響を及ぼしたのだ。内村は世間から国賊視され、内村の家には、一高生が石を投げつけに来る。彼の歴史の教授振りは生気があって面白かったであろうから、彼を敬慕していた学生も少なからずあったのであろうが、彼等も、世間を憚(はばか)って彼に近づかなかったらしい。親戚にも嫌われたらしい。しかも事件後に彼は発熱したのである。流行性感冒から肺炎になったのである。(中略)二度目の愛妻とは、不敬事件の数ヶ月前、すなわち一高の教師になり立ての時結婚したのであった。結婚間もなく変な事件勃発のため、夫人は周囲の迫害に悩まされ、夫の看護に疲労し、その揚句に、感冒に罹って逝去したのである。不幸な生涯である。多感多情の内村が天を仰いで哭するのもさもあるべき事である。その上、キリスト教信者からも攻撃の鉾を向けられた事が記されている。病気の危険期が去って周囲の事に気がつくと、「私はあらゆる仕事が剥奪されてあるのを発見しました。私はキリスト教徒が私に対して臆病ものとその矛を向けているのに気がつきました。私がお辞儀する事を認めたというので、私をおべっか者と呼びました。私自身のみならず、私の家族までが破廉恥ものとされたのです。組合教会の人達はお辞儀することは正しいと支持しながら、私が政府当局に負けたとて軽蔑の言葉をあびせるのです。私一個の事件が基督教団対国家皇室対と、一般的な問題となって来ました。」
(『内村鑑三』)
正宗白鳥は、若い頃内村鑑三に傾倒し、洗礼も受けているが、後年は内村から離れたようで、彼の著した『内村鑑三』『内村鑑三雑感』は、内村鑑三の説くキリスト教と、内村鑑三という人間を懐疑の念を抱きながら書いている。去って行った恋人を思うような、恋しさ半分、憎さ半分と言ったような複雑な思いが文章全体に染み出ていて、それが正宗白鳥の人間味でもあるし、そこに書かれている宗教観なり人生哲学のようなものにも共感することが多い。それはさておき、この不敬事件は、内村鑑三の真価を問うには些細な問題であるが、それでも触れたいと思うのは、私が生きている現在の世の中のありよう、つまり新型コロナ感染症によって起こった世の中の異常なありようと、不敬事件の頃の世の中の様相が重なって感じられるからだ。
正宗白鳥は、内村鑑三の不敬事件を「大山鳴動鼠一匹と云ったような、たよりない次第である。」と冷ややかに書いている。「患難は人生最上の恵みである」(ヨブ記講演)と内村は言うではないか、内村はどうも言行不一致ではないかと言いたいのだ。正宗白鳥はそう思いつつも、「しかし、世の風潮に逆らう事、強者の権威は少しでも逆らうことは並大抵でできる事ではないのである。それは戦争中、人の身の上にでも自分の身の上にでもにがにがしく現れていたではないか。内村が世の中の流れに逆らった彼の行為を徹底したなら、見物人に取っては一層面白かったかもしれないが、徹底的でない所に、《如何にして生きんか》の人間の本能的欲望が現れていて、我々の、いきいきとした参考になるのである。」(内村鑑三雑記)と言っている。私もそう思う。四百数十年前、死を厭わず残酷な迫害を受けてもなお神の救いを信じたキリシタンだからこそ、彼等は聖人と呼ばれるのだ。内村は聖人ではない。内村は弱いからこそ、自ら望んだのではなくキリスト信徒となり、人生に対して誠実であったからこそ、回心の道を歩み始めたのだ。誠実に生きようとすることくらいは、我々凡人にでもできるではないか。だからこそ、内村の起した不敬事件は我々の「いきいきとした参考」になるのである。
教育勅語は、明治憲法発布の翌年、近代国家日本の修身道徳教育の根本規範として天皇の詔勅として発布され、学校では、校長が厳粛に全校生徒に向けて教育勅語を読み上げる奉読式が恭しく行われた。それに対して、堂々ではなくとも、衆人が不遜だと認める態度を取ることがいかに厳しいか。事実彼はそれによって甚大な報いを受けるのである。
この不敬事件は、強権国家だから起きたのではない、一般市民、学生が、個人の思想信条を認めず、天皇陛下に対しての敬礼を強制したのだ。今の社会も同じではないか、マスコミ、一般市民、隣の友人が、食い物屋、飲み屋の営業を止めさせろ、マスクをしろ検温をしろワクチンを打てと眉をつり上げて大騒ぎしている。強権国家なら市民が立ち上がれば倒れるであろうが、市民が無知蒙昧では如何ともし難い、さらに文学者、宗教家、芸術家、学者まで同様では救いようがないのだ。今流行の言葉を使えば、近代国家はテクノロジーだけは進化させてきたが、「リベラルアーツ」の精神はまったく育っていないと言えるのではないか。
『内村鑑三雑感』には次のようにある。内村曰く、「試みに文学者の全部が今日消失するとも、日本人は何の損害も感じない。彼等の間に多くの背教者と堕落信者とが在る。彼等は孰(いづ)れも遊び人である。筆を執って起こる勇者ではない。責任を免れ、唯面白可笑しく一生を終わらんと欲する懶け者である。日本国を亡ぼしつつある者は多々あるが、今の文士と新聞記者が其主たる者である事は疑う事が出来ない。」
正宗白鳥は、これに対し、「例の如き片意地な意見であるが、幾分の信憑性を持っていると思われないこともない。」と言っている。私も時代は違えども、このコロナ下において、「日本国を亡ぼしつつある者は多々あるが、今の文士と新聞記者が其主たる者」と思うのである。※コロナ社会については、店主のブログ「知と愛」に「このうそ寒い世の中へ①~⑤ 新型コロナウイルス感染の流行で思うこと」として綴っておりますので、よろしければお読みになってください。
さて、正宗白鳥の宗教観は、内村鑑三に対立するもの、あるいはキリスト教、というよりも聖書に対立するものとして以下によく表れている。また。それは世間凡人の常識的な感じ方であると思うし、翻って、それが内村鑑三あるいはキリスト教の本質を照らし出すことになると思うので、少し長くなるが『内村鑑三雑感』より引用する。
永遠の神を敬し神を愛し神の奴隷たるに甘んじるのが、キリスト教の立場から云って永遠に生きる道であるが、これも空疎な夢であって真実に徹するのは、容易ではないのである。中世期の信徒などは世俗の生活を厭(いと)い、隣人を厭い、修道院に立て篭もって、神のみ交わるのを是(ぜ)なりとしたのである。自分の一生を人類愛に捧げる特殊な人物も稀には存在しているが我々がみんなそれに見習う訳にも行くまい。癩病院とか白痴院とか孤児院とかに奉職して、無償で勤務して、一生世間的の享楽も栄華も顧みないのは、神の御心に叶う尊い生涯であると云われようが、これ等は万人が真似すべきものではない。私などは、他の何者かのために自己を犠牲にする異常心理に驚嘆することはあっても共鳴はなし得ないのである。神の存在を認識し、神の無限の力に圧倒される時には、神の命には何でもこれ従わねばならぬと、戦々恐惶たる心理を経験さゝれるのであるが、「いかに生くべきか」について考えて、自己の欲望や心身を全部犠牲にして、他人のために盡すことによって、生存の満足、永遠の生命の悦楽境を獲得されるであろうかと疑う。藤堂高虎は主君(徳川家康)の前で髻(もとどり)を切って改宗を誓い、三世に渡る永遠の生命を予定してしまった。高虎のような武士道的人生観所有者は、主君の死ぬる時には、自分も腹掻き切って殉死しなければならぬのだ。喜び勇んで死ぬ筈(はず)である。武士道の残酷性を私はそんな所に見るのであるが、愛の福音の源泉のようなキリスト教にしても、信者をして殉難の苦を余儀なく体験させるような残酷性を有(も)っているのである。日本に於ける徳川初期に切支丹迫害史を読んでもそう思われるのである。永遠の生命を獲得するためには、こうまでしなければならぬと、嗾(けしか)けるような残酷性を私は感じさゝれた。あの頃の信者は、人間の想像し得られないほどの残忍な迫害を受けたのだ。それは死後の天国行きを夢想したゝめに異常の迫害に怯(ひる)まなかったのであったが、萬里の波濤を凌いで、日本に福音を伝えに来た聖者であるキリシタンバテレンは、何故に過酷な迫害を忍ぶように、単純な日本の信徒に智慧をつけたのであろう。火あぶりにされるとか、手足の指を斬られるかするのは、まだしも迫害の初歩として、永遠の生命の交換として我慢し得られるとしても、父母の眼前で幼年少年の兒女が虐殺される事、或いは、夫や父の見ている前で、妻や娘が、癩患者や乞食によって犯される事、そういう迫害を忍んでまで、天国に行かねばんらぬのか。永遠の生命が、こんな犠牲によって得られるのであろうか。私はそれを疑っている。なぜに転向してかゝる苛烈な迫害から免れようとしないのか。神若(も)し慈愛の神ならば、かゝる場合の転向を咎(とが)め給(たま)う筈がないのではあるまいか。永遠の生命がそういう事によって得られるのなら、永遠の生命なんかいらないというのが、自然の人情ではあるまいか。信者が迫害時代に、転向して災難を免れると、死後、転向の罪によって真実正銘の地獄へ追い込まれるのであるか。そうすると信者も立つ瀬がないのである。福音書のうちに、「かゝる艱苦切迫の場合には、転向を装ってもよし、偶像に向かってちょっとくらいお辞儀してもよし。」といったような、憐れみ深いお言葉がキリストの口から出ていたらどうであろうかと、私は思うのである。
東西の歴史が證明しているが、宗教的残虐性は人間の残酷姓のうちで最も激烈なるものである。私は、『内村鑑三』と『内村鑑三雑感』を通読して、正宗白鳥のキリストへの不満は、旧約聖書にある『ヨブ記』に書かれたヨブの神への不満と同じように感じられないでもなかった。『ヨブ記』は、ヨブという、神の眼から見ても、正しき人(義の人)であり、神を畏れ敬い、非のうちどころのない、善良で実り豊かな暮らしをしている人間が、神によって次々と残酷な試練をあたえられ、真の回心にいたる物語である。もちろん、正宗白鳥の神あるいはキリストへの信仰が、ヨブのような苦難に満ちたものであったはずはない。元より『ヨブ記』は、正宗白鳥の言葉を借りれば「夢物語」なのである。私は、正宗白鳥の信仰について深く知り得ないが、自身の問題として、「全能の神の前に責任を負う霊魂」(『余は如何にして基督信徒となりし乎』)ということを、生涯を通して考えていた人であろうと思う。それは、内村の言葉を借りれば「神に捉えられた証拠」(ヨブ記講演)でもある。
私は、人生の半ば40歳くらいまでは、無神論的な気分で生きていた。人間は死んで燃やされたら灰になるだけだ。もっと若いころは神仏を拝むということも拒否していた。いただきますと手を合わせることも嫌だった。しかし、書画の仕事を私なりに深めていくうちに、そういう自分がつまらなく思えてきた。今となって信仰とは考えることが先ではないことがなんとなくわかってきた。神は我々が生まれる以前より在(ましま)すのだ。それを確固として感じられなかったら内村の言うことも言葉づらでしかわからない。と、それでも、今なを私は、神を畏れるとはどういうことか、神を信じるとはどういうことか、あれやこれやと宗教について考える。私はとても神にも仏にも近づくことができそうにないのである。(店主記)